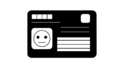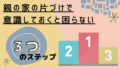こんにちは(^_^)
アラフォーでオヤカタ(親の家の片付け)を始めたパピンです。
親の家の片付けに本腰を入れてから1年が経ちました。
片付け当初、私が感じていた疑問。
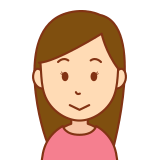
片付けが長期に渡っていて先が見えない
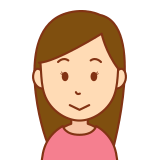
これから親の家の片付けを始めたいけれど、何から始めればいいかわからない
こんなことで困っている方はいませんか?
本日の記事では、1年間の片付けを経たパピンが感じた、親の家の片付けをスムーズに進める方法をお伝えしたいと思います。
生前整理は時間がかかることを前提に
まず、今回お伝えする片付けは「親御さんが健在である(遺品整理ではない)」「引っ越しを控えていない(介護施設等への移動のための片付けではない)」ことを前提としています。
いわゆる、子供が親のために行う生前整理。
親御さんご自身が行う生前整理でも同じことが言えると思いますが、とにかく時間がかかることを覚悟の上で行いましょう。
なぜなら、期限が設けられている遺品整理や施設への引越しを控えている場合でない限り、普段の生活をしながら整理の時間を設けるのは難しいからです。
その理由の一つは、親の体力の無さ。
そしてもう一つは、子供の時間の無さです。
もちろん気力・体力共に元気な親御さんをお持ちの方もおられると思いますが、大抵は持病があったり、体のあちこちが故障気味だったり…なんらかのトラブルを抱えている親御さんは多いでしょう。
普段の暮らしの中で、今までになかった「物を整理する」という作業が付加されるのは、心身への負担がとても大きいものです。
「捨てる、残す」の判断作業にも時間がかかります。
加えて子供世代は、仕事・家事・育児と毎日が目まぐるしいスケジュールの中で動いており、そこに親の家の整理が加わるとなると、どう時間を捻出するかが難問。
「時間をかけて少しずつやっていく」という選択肢しか残りません。
・1日の中で、小さな箇所(たとえ引き出し一つでも)をできれば良しとする。
・期限を設けず気長にやる。
というスタンスでやっていかないと、すぐに嫌気が差してしまうでしょう。
少しずつやるというのは、マイナスな見方をするとダラダラやっていくとも受け取れてしまいますが、それくらいで丁度いいのです。
なぜなら、片付けを一気にやってしまうと、その変化についていけない親御さんが不安な気持ちに苛まれるためです。
若い時には耐えられた急激な環境変化は、年を取ると好まなくなっていくもの。
少しずつ進めていくことで物が整理されていくことに慣れていく過程が必要なのです。
片付けをする子供の側からすると、やってもやっても終わらない感に焦りや苛立ちを覚えることも多々ありますが、「いつかは終わる」という心構えを持ちながら進めていくことをおすすめします。
親が生きているうちに片付けるメリット・デメリット
遺品整理とは違い、親が健在なうちに行う片付けにはメリット・デメリットがあります。
・メリット
親と共に確認しながら進められる。
大事な物を捨ててしまう事故が少ない。
認知症を発症する前に通帳や保険書類などの大切な物の保管場所を一緒に確認・整理ができる。
・デメリット
捨てたくないものが多い場合、片付けが中々進まない。(次章で詳しく説明)
各ご家庭によりメリット・デメリットは多少異なると思いますが、把握しながら進めると、それぞれの対処方が見えてきてより片付けがスムーズになります。
親が他界してからでないと手をつけられない物を知る
先に述べたデメリットについてですが、物を捨てる・処分することに慣れていない親御さんの中には「まだ使えるから」「これは高かった」「あの時の思い出の品だから」と、物を手放すことを拒否される方も多いと思います。
我が家は父が特にその傾向が強く、この1年で何度か衝突がありました。
特に処分したがらない物のジャンルでいうと、
・思い出関係(アルバム、祖父母の遺品など)
・不動産関係
・書籍・資料関係
・自分の日記
残される側としては、処分するのに面倒な物ばかりなので早くやって欲しい…という思いはあるのですが、これらは両親が他界した後に片付ける物なのだとあきらめて、そのままの状態にすることを受け入れています。
効率よく片付けるために順位付け
以上を踏まえると、自ずと家の中の片付け優先順位が決まってきます。
たとえば、
・備蓄ストック型の親の場合は、消耗品関係から手をつける。
(私は納戸から片付けを始めました)
【1F納戸_DAY2】納戸ミュージアム!?食品ロス問題を考えさせられた日。
・親が処分したがらない物は後回しにする。
(説得に時間をかけるよりも、先に出来ることから手を付けた方が効率よく進められます)
また、両親に片づけて欲しい場所をヒアリングするのも一つの方法。
我が家は母が片付けに前向きだったため、やって欲しい場所を事前に聞きながら進めました。
当時はまだ同居の話が出ておらず、体が不自由になってきた母が台所の使い辛さを訴えていたため、吊り戸棚の整理から始めました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
これから始めるという方も、既に始められている方も、各ご家庭により事情は様々かと思いますが、私が伝えたいことは、
・とにかく無理をしない
・時間がかかることを前提にやる(先を急がない)
ということです。
家の明け渡し期限があるのであればそのスケジュールに合わせなくてはなりませんが、そうでなければ細く長く続けられるよう親子共々無理の無い範囲で進めることが大切です。
片付けが原因での両親との衝突は心身ともに摩耗します。
(親の方も疲弊してしまいます)
両親の残りの人生を暮らしやすくするために、そして残される子供の私たちが親の家の片付けで苦労しないために、今から少しずつ始めていきましょう。
本日もお読み下さり、ありがとうございました(ー人ー)